-

令和2年の恵方巻きの方角は?(2020年)
令和2年の恵方巻きの方角は?(2020年) 平成31年(2019年)2月3日の節分は西南西です 恵方巻きってなに? 七福神にちなんだ7種類の具材をいれ、縁起を担いだのり巻きです 代表的な ...
-
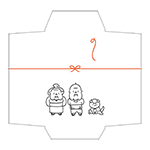
ポチ袋
ポチ袋7種類セット おじいちゃんのポチ袋 おばあちゃんのポチ袋 ポチのポチ袋 全員集合のポチ袋 黄のポチ袋 緑のポチ袋 青のポチ袋 下のzipをDLして、印刷、カットして組み立ててお使い ...
-

七十二候(2018)
陸月(むつき) 小寒(しょうかん) 1月5日 芹乃栄 1月10日 水泉動 1月15日 雉始雊 大寒(だいかん) 1月20日 款冬華 1月25日 水沢腹堅 1月30日 鶏始乳 ...
-

立秋(りっしゅう)
暦の上では秋の始まり。 立秋とは 二十四節気・十三番目の季節「立秋」。立春から数えて、十三番目にあたるのが、この「立秋」です。 秋のくくりのトップバッターですが、日本列島はまだまだ暑いころ。お祭りや、 ...
-

小暑(しょうしょ)
梅雨明けの待ち遠しいころ。 小暑とは 二十四節気・十一番目の季節「小暑」。「立春」から数えると、十一番目に巡ってくるのが、この「小暑」です。 夏のくくりでいうと、もう最後から二番目になります。 小暑の ...
-

小満(しょうまん)
そろそろ夏の便りの届くころ。 小満とは 二十四節気・八番目の季節「小満」。「立春」から数えると、八番目に巡ってくるのが、この「小満」です。 小さく満たすと書いて、「しょうまん」と読みます。 「二十四節 ...
-

冬至(とうじ)
1年の中で最も、日の短いころ。 冬至とは 「立春」から数えて、二十二番目に巡ってくるのが「冬至」です。 「とうじ」という言葉を聞いたこともあるかもしれませんが、二十四節気では、その日1日ではなく2週間 ...
-

大雪(たいせつ)
寒さが本格的になりはじめるころ。 大雪とは 「立春」から数えて、二十一番目に巡ってくるのがこの「大雪」です。 「おおゆき」ではなく、「たいせつ」と読みます。 大雪の持つ意味とは 「二十四節気」には「大 ...
-

小雪(しょうせつ)
日に日に、冬の深まるころ。 小雪とは 「立春」から数えると、二十番目に巡ってくるのが、この「小雪」です。 「こゆき」ではなく、「しょうせつ」と読みます。 ちなみに「こゆき」と読む場合、天気予報などでい ...
-

立冬(りっとう)
だんだん寒さが身にしみてくるころ。 立冬とは 二十四節気・十九番目の季節「立冬」 二十四節気も冬のくくりへと突入です。トップバッターは、立春や立夏、立秋などと同じく四立の一つです。「立春」から数えると ...
-

霜降(そうこう)
秋も深まり、次第に冬を感じるころ。 霜降とは 「立春」から数えると、十八番目に巡ってくるのが、この「霜降」です。 「しもふり」ではなく、「そうこう」と読みます。 霜降の意味とは 「霜降」は、読んで字の ...
-

寒露(かんろ)
中秋の名月を眺めるころ。 寒露とは 「立春」から数えると、十七番目に巡ってくるのが「寒露」です。 「かんろ」と読みます。 寒露の持つ意味とは 寒いに露(つゆ)で、「寒露」とよみます。 ー夜の冷え込みが ...
-

秋分(しゅうぶん)
秋の訪れを感じるころ。 秋分とは 「立春」から数えると、十六番目に巡ってくるのが、この「秋分」です。 秋のくくりのなかでは真ん中に位置し、季節的にもいろいろなイベントのころになります。 「秋分の日」は ...
-

処暑(しょしょ)
暑さは暦よりもう少し残るころ。 処暑とは 二十四節気・十四番目の季節「処暑」。立春から数えて、十四番目にあたるのが、この「処暑」です。 「しょしょ」と、読みます。 秋のくくりのなかでは二番目に巡ってき ...
-

大暑(たいしょ)
夏が本格化してくるころ。 大暑とは 二十四節気・十二番目の季節「大暑」。「立春」から数えると、十二番目に巡ってくるのが、この「大暑」です。 夏のくくりはこれで最後ですが、季節的にはまだ暑くなったばっか ...